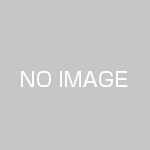読売新聞 4月29日 一面には、ジョセフ・ナイ教授の「露のサイバー攻撃 報復警告と外交で対処」が掲載されています。
読売新聞のナイ教授の記事としは、2017年5月1日の「サイバーと倫理」、2018年8月26日 「 露のサイバー攻撃 戦闘伴わぬ「新兵器」」 に継ぐものかと思います。
内容としては、
1)2016年のロシアの大統領選に対するサイバー攻撃に対しては、効果的な対応ができなかった
2)この状況が変わってきている。
3)2018年中間では、ロシアの情報工作を阻止したこと
4)ハイブリッド戦争のようなグレーゾーンでも抑止を強調するドクトリンは、有効であること
5)経済制裁・渡航禁止措置は、有効であること
6)外交も必要となること
7)特定の種類の民間施設に対する攻撃に制限をもうけ、衝突の危険を極小化する大まかなルールの交渉は可能であること
8)現状は、民主主義的な開放性を米国のほうが、失うものが大きいこと
9)「米国が順守を誓い、ロシアが違反してきた規範はどれなのかをずばり明らかにする」べきという議論に賛成すること
10)公開のプログラムと放送は、容認されるが、隠密の組織的活動を通じた自己宣伝は、拒否すること
あたりでしょうか。
特に昨年の同名の論考(サブタイトルが、戦闘伴わぬ「新兵器」)から、比較すると、具体的な対抗措置の有効性について考察していることと、具体的な規範について考察し、今後の方向性を示唆している点で非常に興味深いと考えます。
9)についていうと、伝統的なエスピオナージの理論と現代的な情報の限界をどこに置くかというのは、国際法の文脈でも議論されてきていたことは、このブログでも触れています。特に、タリンマニュアル2.0 パネルのエントリの質疑応答が参考になります。そこを再度引用しましょう。
1:24-)DNCについては、
(シュミット)国際法のグレイゾーンとして興味深いエリアだといえます。というのは、シュミット先生の見解によると、「国際法における禁止されている干渉」の問題と考えられるからです。これは、国際法は、主権国家は、他の主権国家の「Domaine Reserve」といわれる部分に強制的な方法(coercive manner)で、干渉することは禁止されています。これに対して、エスピオナージは、国際法の違反には該当しないとされます。マニュアルでは、この点を描こうとしています。ここで、「強制的」(coercion)とは何かという問題になります。これについては二つの見解があります。一つはLiis先生の見解で、今一つは、シュミット先生の見解です。他国の民主国家に対する情報提供はすべて適法であるという考え方も存在し得ますが、シュミット先生の見解としては、この点は、ラインを超える場合のみが、この場合に該当するという見解です。超える場合としては、「過程を操作してしまう場合」については、国際法の違反と考えることができるという立場です。(追加・ロシアは)意図的にファジーな状態にしているので、法的には、「優秀な」法律家といえるでしょう。
この「ラインを越える場合」というのは、どのような場合をいうのか、という問題について、ナイ教授は、「隠密の組織的活動」を、国際的に違法とするべきだと主張していると理解しました。するとこの場合の要件は、「隠密性」と「組織性」になります。国内法における言論の自由市場の考え方も、隠密な、組織活動が違法となることを否定しないでしょうから、まさに、国際法と国内法の次元の裂け目(アベンジャーズか、ドクターフーか)を塞ぐ解釈になるかと思います。